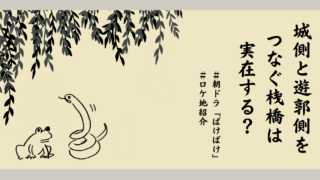NHK朝ドラ「ばけばけ」第1話で、主人公一家が「武家の世の終わり」を呪い、深夜に「丑の刻参り」をする場面が描かれました。
突然現れた不気味な儀式に驚いた視聴者の中には、
- 「丑の刻参りって実際にあったの?」
- 「いつの時代の風習?」
- 「藁人形を打つイメージはどこから来たの?」
と疑問を持った方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「丑の刻参り」の意味や実際の時代背景を整理し、ドラマのシーンが持つ歴史的リアリティを解説します。
☞☞ばけばけについて詳しく知る!!
この記事で分かること
- 丑の刻参りとは何か?
- いつの時代に行われていた?
丑の刻参りとは何か
「丑の刻参り(うしのこくまいり)」とは、日本の民間信仰における呪術的な習俗の一つです。
丑の刻とは
- 昔の時刻制度では、1日を十二支に分けて表していました。
- 「丑の刻」は午前1時から3時頃を指します。
- 人々が眠りにつき、街も静まり返る時間帯であるため、「霊力が強まる時」と考えられていました。
儀式の方法
- 深夜の丑の刻に神社へ赴く。
- 憎む相手を模した藁人形を用意する。
- その人形を神木に五寸釘で打ちつけ、怨念を込める。
この行為によって、呪いたい相手に不幸や病をもたらすと信じられていました。
藁人形や五寸釘のイメージは、江戸時代の絵画や随筆で多く描かれたことから、現代でもホラー表現の定番になっています。
丑の刻参りはいつの時代に行われていたのか
平安時代に見られる起源
- 平安時代の文学には「丑の刻詣で(丑の刻に神仏へ強く祈る行為)」と呼ばれる習俗がすでに登場します。
- 『源氏物語』や『今昔物語集』などには、深夜に神仏へ強い願いをかける女性の姿が描かれています。
当初は必ずしも「呪い」だけでなく、恋愛成就や強い祈願のために行われることもありました。
室町〜江戸時代にかけての定着
- 室町時代頃から、怨霊を呼び起こす呪詛の儀式としての性格が強まります。
- 江戸時代には「丑の刻参り」という名称と具体的な方法が広まりました。
- 随筆「耳袋」や浮世絵に「藁人形を打つ女」の姿が描かれ、庶民文化に定着。
実際に丑の刻に神社で人形を打つ行為が問題視され、処罰の対象になった記録もあります。
明治以降の位置づけ
- 近代化の中で迷信として衰退し、現実に行う人はほとんどいなくなります。
- しかし文学や怪談、さらに現代の映画・ドラマ・漫画の題材として語り継がれています。
- 今日の私たちが持つ「恐ろしい呪いの儀式」というイメージは、江戸時代以降に固まったものです。
「ばけばけ」での描写と時代背景
「ばけばけ」の冒頭で主人公一家が丑の刻参りを行ったのは、「武家社会の終焉」を呪うという場面でした。
社会の不安を象徴する儀式
- 実際の歴史でも、時代の変わり目や社会不安の高まりといった局面で、人々は神仏や呪術に頼ることがありました。
- 政権の移り変わりや生活基盤の喪失は、恨みや恐怖を呼び、それが「丑の刻参り」のような習俗に投影されたのです。
ドラマでの意味合い
- 主人公一家の行為は、単なる迷信の再現ではなく、当時の人々が抱いた切実な感情を象徴しています。
- 怨念や呪詛は、物語を貫く「時代の影」を浮かび上がらせる演出として機能していると言えるでしょう。
ドラマの予備知識を深めるのにぴったり✨
現代に伝わる丑の刻参りのイメージ
現代では、実際に丑の刻参りを行う人はほとんどいません。
しかし、
- 怖い話の題材
- ホラー映画や漫画の演出
- 神社に残る伝承
などを通じて「藁人形」「五寸釘」「深夜の神社」といったイメージが受け継がれています。
「ばけばけ」のシーンに視聴者が強い印象を受けたのも、この文化的イメージが現代に深く根付いているからでしょう。
まとめ
- 丑の刻参りは、平安時代の「丑の刻詣で」を起源とし、室町〜江戸時代にかけて呪術的習俗として広まった。
- 江戸時代には「藁人形を五寸釘で打つ」という形で庶民文化に浸透し、恐れと関心を集めた。
- 明治以降は衰退したものの、現代では怪談やフィクションを通じて強烈なイメージを残している。
- 「ばけばけ」第1話での描写は、時代の不安や怨嗟を象徴するものであり、歴史的背景を知ることで物語の深みが増す。

朝ドラ『ばけばけ』のナレーションは誰?蛇と蛙の正体と役割を徹底解説
朝ドラ『ばけばけ』を見ていると、独特な“語り”に気づいた方も多いはず。定番の「語り手」の声ではなく、CGで登場する蛇と蛙が物語に絡んでくるのです。では一体、誰が声を担当しているのか?なぜ蛇と蛙なのか?その疑問を整理してみました。この記事で分...

「武士の時代の終わり」とは?朝ドラ『ばけばけ』をもっと楽しむために時代背景を解説
朝ドラ「ばけばけ」に出てくる武士の時代がどんな社会だったのか、なぜ終わったのか、そして武士たちはその後どう生きたのかを、歴史的事実をもとに解説します。

朝ドラ『ばけばけ』のモデルは誰?あらすじやヒロインを紹介
2025年後期NHK朝ドラ『ばけばけ』が9月29日からスタート!怪談好きのヒロイン・髙石あかりさんやあらすじ、豪華キャスト情報をまとめました。